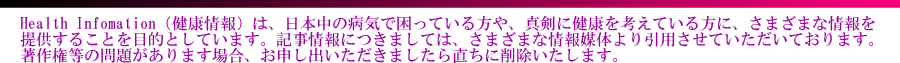2011年2月10日
東京大学大学院 工学系研究科 マテリアル工学専攻
大学院医学系研究科 疾患生命工学センター 臨床医工学部門
片岡一則教授
がん治療の柱の一つである抗がん剤。現在、「第3世代」と称される抗がん剤が使われるようになり、有効性に関するエビデンスも出始めている。一方で、患者の多くは、相変わらずひどい副作用に苦しんでいる。吐き気などは制吐剤によりある程度コントロールできるようになっているが、脱毛や味覚障害、末梢神経障害など、「生活の質(QOL)」を著しく低下させるさまざまな副作用がみられるためである。こうした副作用は、抗がん剤を全身に投与することで、その毒性が全身にあらわれるために生じる。回避するには、薬を局所にピンポイントで送り込むDDS(Drug Delivery System)の開発が不可欠とされる。このほど、東京大学大学院 工学系研究科 マテリアル工学専攻と大学院医学系研究科 疾患生命工学センター 臨床医工学部門を兼任する片岡一則教授は、高分子ミセルのナノカプセルを利用することで、大腸がんのがん細胞中にピンポイントで薬を送り込むことに成功した。
片岡教授らが用いた高分子ナノミセルは、直径50ナノメートルほどの中空の球体。高分子ミセルとは、ポリエチレングリコールなどの親水性ポリマーとポリアミノ酸誘導体などの疎水性ポリマーを水中で自己組織化させたもので、球表面に親水性ポリマーが、内側に疎水性ポリマーが位置する二層構造をもつ。このような高分子ミセルは、脂質二重膜からなる細胞膜の表面に結合し、エンドサイトーシスによって細胞膜ごと細胞内に入り込むことができる。
今回、片岡教授らは高分子ミセルの中空部分に、進行した大腸がんの標準的な治療に用いられるオキサリプラチンという抗がん剤を入れた。それを「尻にヒトの大腸がんを植え付けられたマウス」の尾の静脈から注入した。「投与直後は高分子ミセルが血中を安定して循環し、薬剤は放出されなかった。約12時間後になると、血中を循環する一方で一部ががん組織中のがん細胞に取り込まれ、細胞内で薬剤を放出しはじめた。その結果、がんは通常の方法で全身投与した場合の5分の1程度に縮小した」と片岡教授。
工学出身の片岡教授は、1980年代後半に「がん組織では血管を流れる粒子が流出しやすく、そのような粒子はがん組織中に取り込まれて蓄積しやすい」との知見がもたらされたことをきっかけに、抗がん剤のDDS研究をはじめたという。まず、細胞に取り込まれやすいのは、直径が50ナノほどの大きさの粒子であることを突き止めた。そして、このようなナノカプセルを作るにはウイルスのような「生物が本来もつ自己組織化」を用いるのがよいこと、血液の凝固を防ぐにはカプセルを生体適合性の高い分子で包めばよいことなどを明らかにしていった。「1987年に動物実験をはじめ、1988年には肺がんで縮小効果があることを実証できた。現在は、パクリタキセルという抗がん剤でフェーズ2の治験が終わり、フェーズ3への準備に入っている段階。それ以外にも2剤で治験が進められている」と片岡教授。
抗がん剤治療では、全身投与を繰り返すうちに、がん細胞がその抗がん剤に対する耐性を獲得し、次第に効きが悪くなっていく点も問題視されている。「私たちの方法では、がん細胞が抗がん剤だと知らずに高分子ミセルを取り込むので耐性が獲得されることはない」。片岡教授はそうコメントしたうえで「このようなDDSは、いつでも・どこでも・誰にでも実施可能で、とくに大きな装置や設備は必要なく、入院不要で副作用対策費もいらない。大幅な医療費の抑制にもつながる」と続ける。
すでに日本、米国、フランス、英国、台湾、シンガポールなどでは、製薬企業主導のもと、高分子ミセルによる抗がん剤治療の治験が行われている。一般の治療として用いられるようになれば、副作用の軽減やQOLの改善だけでなく、患者の余命を大幅に延長できると期待できる。「DDSは人体というミクロコスモスにおけるアポロ計画といえるだろう。私は、がんだけでなくアルツハイマーやパーキンソン病などにも使えるナノデバイスを開発したい。さらに、それらを用いて、体内での分子レベルの事象を時間と空間を制御した形で解き明かし、ナノ生理学とでもいうべき分野を構築したい」と意気込む片岡教授。工学と医学、応用研究と基礎研究の各領域を行き来する日々が続く。
(nature japan)
|
|